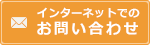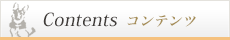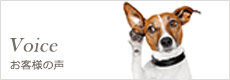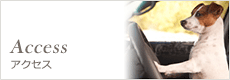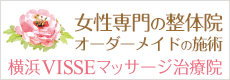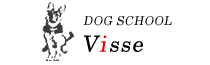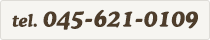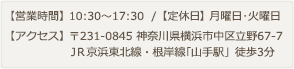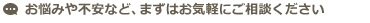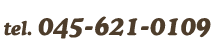月別 アーカイブ
- 2025年7月 (16)
- 2025年6月 (25)
- 2025年5月 (26)
- 2025年4月 (22)
- 2025年3月 (23)
- 2025年2月 (22)
- 2025年1月 (23)
- 2024年12月 (24)
- 2024年11月 (28)
- 2024年10月 (28)
- 2024年9月 (28)
- 2024年8月 (19)
- 2024年7月 (27)
- 2024年6月 (28)
- 2024年5月 (26)
- 2024年4月 (21)
- 2024年3月 (26)
- 2024年2月 (24)
- 2024年1月 (21)
- 2023年12月 (23)
- 2023年11月 (24)
- 2023年10月 (23)
- 2023年9月 (23)
- 2023年8月 (17)
- 2023年7月 (26)
- 2023年6月 (14)
- 2023年5月 (22)
- 2023年4月 (26)
- 2023年3月 (24)
- 2023年2月 (26)
- 2023年1月 (19)
- 2022年12月 (23)
- 2022年11月 (22)
- 2022年10月 (21)
- 2022年9月 (15)
- 2022年8月 (18)
- 2022年7月 (23)
- 2022年6月 (26)
- 2022年5月 (21)
- 2022年4月 (18)
- 2022年3月 (25)
- 2022年2月 (22)
- 2022年1月 (20)
- 2021年12月 (26)
- 2021年11月 (27)
- 2021年10月 (23)
- 2021年9月 (20)
- 2021年8月 (13)
- 2021年7月 (20)
- 2021年6月 (20)
- 2021年5月 (19)
- 2021年4月 (25)
- 2021年3月 (27)
- 2021年2月 (21)
- 2021年1月 (19)
- 2020年12月 (23)
- 2020年11月 (28)
- 2020年10月 (22)
- 2020年9月 (15)
- 2020年8月 (16)
- 2020年7月 (25)
- 2020年6月 (24)
- 2020年5月 (18)
- 2020年4月 (19)
- 2020年3月 (21)
- 2020年2月 (18)
- 2020年1月 (16)
- 2019年12月 (25)
- 2019年11月 (20)
- 2019年10月 (22)
- 2019年9月 (23)
- 2019年8月 (16)
- 2019年7月 (26)
- 2019年6月 (29)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (14)
- 2019年3月 (20)
- 2019年2月 (16)
- 2019年1月 (15)
- 2018年12月 (13)
- 2018年11月 (17)
- 2018年10月 (17)
- 2018年9月 (10)
- 2018年8月 (10)
- 2018年7月 (16)
- 2018年6月 (12)
- 2018年5月 (12)
- 2018年4月 (17)
- 2018年3月 (21)
- 2018年2月 (13)
- 2018年1月 (12)
- 2017年12月 (8)
- 2017年11月 (11)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (21)
- 2017年8月 (11)
- 2017年7月 (15)
- 2017年6月 (12)
- 2017年5月 (12)
- 2017年4月 (16)
- 2017年3月 (16)
- 2017年2月 (10)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (12)
- 2016年11月 (10)
- 2016年10月 (10)
- 2016年9月 (12)
- 2016年8月 (10)
- 2016年7月 (13)
- 2016年6月 (18)
- 2016年5月 (18)
- 2016年4月 (19)
- 2016年3月 (13)
- 2016年2月 (15)
- 2016年1月 (15)
- 2015年12月 (16)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (14)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (13)
- 2015年6月 (15)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (23)
- 2015年3月 (15)
- 2015年2月 (15)
- 2015年1月 (13)
- 2014年12月 (12)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (18)
- 2014年8月 (9)
- 2014年7月 (12)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (12)
- 2014年4月 (16)
- 2014年3月 (12)
- 2014年2月 (8)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (8)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (6)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (6)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (1)
- 2012年2月 (1)
- 2012年1月 (1)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (1)
- 2011年7月 (1)
- 2011年5月 (2)
- 2011年4月 (1)
- 2011年1月 (2)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (2)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (1)
- 2010年7月 (4)
- 2010年6月 (2)
- 2010年5月 (1)
最近のエントリー
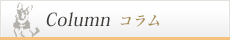
HOME > Visse's Blog > アーカイブ > エッセイの最近のブログ記事
Visse's Blog エッセイの最近のブログ記事
横浜市の犬のしつけレッスン/たくさん褒めて犬の行動を強化しよう
■たくさん褒めて犬の行動を強化しよう
強化とは、「ある行動が増えた状態のこと」を言います。犬(人も)の良い行動を強化するには、必ず良いことが起きなければなりません。この強化の仕方には、以下の3種類があります。
1.正の強化
犬に「スワレ」や「マテ」などをさせて、出来たら褒めたりオヤツをあげたりするのが、この正の強化です。いわゆる、一般的な褒めてしつけるというのがこれです。
2.他行動強化(行動の肯定)
犬が大人しく良い子にしていたら、当たり前と思わず褒めてあげることです。例えば、ケージの中で吠えている犬がいるとします。犬が吠えた時に大抵の方が叱ると思います。しかし、その後、犬が大人しくしている時に、褒める方はいないのではないでしょうか?いくら叱っても良い行動は増えません。
しつけの基本は、叱って悪い行動を減らそうとするのではなく、良い行動を強化して増やすことです。そして、良い行動は褒められることで増えていきます。ヴィッセのしつけで一番多く使うのが、この他行動強化です。☞1日100回褒める
3.対立行動強化
散歩中に他の犬に吠えかかる犬がいるとします。犬とすれ違う間、「アイコンタクト」をしたり、「待って」をさせたりして、吠える以外の行動を促すことです。吠える事と他の行動をさせるということが対立していますね。
~まとめ~
1.多くの飼い主が「ノー!」と、間違いを叱るだけで、正解を教えない。
2.しかし、犬を叱るだけでは、良い行動は身に付かない。
3.したがって、同じことに対して永遠に叱り続けなければならない。
4.しつけの基本は、ひたすら良い行動を強化して身につけさせること。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年7月10日 21:14





横浜市の犬のしつけ教室/犬とのコミュニケーションの取り方

私達が小さい時から聞いたり、読んだりしてきた物語あるいは、テレビや映画の中に登場する犬たちは、飼い主にとても忠実で擬人化されて描かれています。そんなイメージが強いせいか、多くの方が犬に言葉が通じると思い、言葉で言い聞かせようとします。
例えば、リードを引っ張る犬に「引っ張らないで!」とか、怖がっている犬に「落ち着いて」などと、言い聞かせようとしても犬は理解できません。なぜなら犬は、言語というコミュニケーション手段を持たないからです。
犬が人に話しかけられている時に気にしていることは、何を言っているかではなく、どういう風に言っているかなのです。犬は、人の声の調子を、ピッチとトーンで聞き分け音声としてとらえています。速くて高い声の時にはテンションが上がり、逆に、低くてゆっくりとした声にはテンションが下がります。
そうして飼い主の声に隠れる気持ちを感じ取っているのです。犬とのコミュニケーションの取り方で大切なことは、
①犬の名前を呼ぶ ⇒ 良いことや楽しいことが起きる前ぶれ
②犬が「なあに?」と飼い主の目を見る ⇒ 飼い主に意識が向く
③して欲しいことを伝える ⇒ スワレやオイデなどの行動
これがコミュニケーションの原則です。でもこれって人も同じですよね?しかし、多くの飼い主の方が、「太郎スワレ」「次郎スワレ」という具合に、犬の名前と指示をセットにしています。
犬は、「なあに?」と反応する暇がないので、飼い主の顔を見上げるようにはなりません。もうひとつのミステイクは、ほとんどの方が犬の顔を覗き込んで指示を与えようとすることです。
飼い主が犬の顔を覗き込む習慣がつくと、犬は見上げる必要がないのですから、これもおやつがない限り、飼い主を見上げる習慣はつきません。こうして、飼い主は知らず知らずのうちに、犬が飼い主を見上げなくてもいい習慣をつけているのです。
人も相手の名前を呼んで、相手の意識がこちらに向かなかったらコミュニケーションは永遠に始まりません。どうでしょうか皆さん?愛犬とコミュニケーションがきちんと取れていますか?独り言になっていませんか?
(DOG SCHOOL Visse)
2025年6月25日 19:59





横浜市の犬のしつけレッスン/犬のしつけは何の為?

犬のしつけは何のために行うのでしょうか?「訓練所に預けたけど、帰ったら元に戻った」 「本を何冊も読んだけど、上手くいかなかった」「しつけ教室に通ったが、トレーナーの言うことは聞くけど、私のいうことは聞かない」」など、こういう話をよく耳にします。
何故こういうことが起きるのかというと、↑の方々に共通していることは、「何のためにしつけをするのか?」という目的(ゴール)がないまま、しつけやトレーニングを行っているからだと思います。
別なことで例えれば、「英会話教室に通ったけど全然喋れるようにならなかった」と言われる方も、そこに目的や必要性がないからです。しつけの目的は、それぞれの飼い主によって違うと思います。「自分が不安だから」 「周りに迷惑をかけないため」 「快適に暮らす為」など・・・。
そして、その答えは、貴方自身が自分で考えて出さなければならない答えなのです。他人に聞いても答えられない問題なのです。なぜなら愛犬と暮らしているのはあなたであり、飼い主も犬も、生活環境も他の方とはすべてが違うからです。
僕も日中、犬を預かってレッスンをするので、「犬を預けると先生のいうことは聞いても、飼い主のいうことは聞かないのではないでしょうか?」という質問はよく受けます。
以前、ご夫婦で問題行動のカウンセリングを受けられた奥様から、同じ質問を受けました。すると、傍にいたご主人がすかさず、「もしそうなったら、俺たちが駄目だってことだよ」と、奥様に言ってくれたのです。僕は思わずご主人に拍手をしてしまいました。
しつけ教室は「基礎」を学ぶところです。私がどんなに犬をトレーニングしても、飼い主がトレーナーから学んだことを、日常生活という「応用」の場で「実践」できなければどうにもなりません
そして、自分が愛犬になったつもりで、「自分の生きがいは何だろう?」ということも考えてみて下さい。「ご飯を食べること」 「散歩に行くこと」 「ボールを追いかけること」 「友達に会うこと」
なんだか禅問答のようになってしまいましたが、これらの疑問に対する答えはひとつではありません。何故なら100の家庭があれば、100通りの暮らし方があるのですから。そして、その答え一つひとつをじっくりと探してみてください。
※ちなみに私の答えは、「誰からも愛され、どこに出しても恥ずかしくない子に育てる為」です。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年6月17日 09:14





横浜市の犬のしつけレッスン/防御性攻撃行動と不安性攻撃行動

防御性攻撃行動は、縄張り性攻撃行動とも呼ばれています。その縄張りは、通常「家」や「庭」または、「車の中」であったりしますが、お散歩などで他の犬や人に対して吠えている場合は、飼い主が縄張りの対象となります。一般的に言う無駄吠えです。
これらの縄張りに近づこうとする人や犬に、威嚇して吠えたり咬んだりして攻撃的に家族や自分を守ろうとすることが、防御性攻撃行動の大きな特徴です。
また、不安や恐れに基づいた攻撃行動として、いきなり頭を触ろうとしたり、抱っこしようとしたり、または足を拭く時やブラッシング、首輪やハーネスの着脱等で体を触ろうとする飼い主に対して唸ったり、更には咬みついたりして自分を守ろうとする不安性攻撃行動と呼ばれる攻撃行動も存在します。
これらの行為が顕著な犬に共通していることは、生まれつき不安や恐怖心が強い犬ですが、日常生活または、社会生活に相当な制限を受ける場合は、※全般性不安障害の可能性があります。
※発達障害、知的障害、精神障害、その他の心身機能の障害など。
【防御性攻撃行動が発達すると考えられる要因】
☑遺伝的要因 ☑現在の環境的要因 ☑社会化不足 ☑犬の性質 ☑散歩不足 ☑飼い主の犬への不適切な接し方 ☑飼い主のリーダーシップ不足 ☑飼い主の行動と性格 ☑問題に対する飼い主の不適切な対処
【改善に必要とされる期間】 3ヶ月~6ヶ月(飼い主の生活環境の改善による)
【改善の為にやらなければならないこと】
(1)散歩が足りていない場合、1日2回(最低30分)の散歩と十分な運動を与え、ストレスとエネルギーを発散させることで、「心」と「体」 のバランスを整え心身ともに満足させる。
※とくに全般性不安障害には、ドッグスポーツが効果的という研究結果が、アメリカのタフツ大学獣医学とNPO団体ケーナイン行動研究センターの研究チームから発表されている。犬の自然な本能に働きかける活動が犬をリラックスさせ、不安が減少すると研究者は述べています。
(2)テキストの「日常生活で行う3つのこと」 「アイコンタクト」 「一時待機の待って」を毎日実践する。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年6月13日 10:51





横浜市の犬のしつけレッスン/しつけと訓練の違い
 先日、いつもの公園でのこと。2頭の小型犬が並んで座っていた。その20メートル程先に飼い主が立っていて、「待て」のハンドシグナルを出している。2頭とも微動だにしない。そして、飼い主が1頭を呼び寄せた後に、もう1頭を呼び寄せたのである。う~ん、2頭別々の「呼び戻し」は、なかなか出来るものではない。
先日、いつもの公園でのこと。2頭の小型犬が並んで座っていた。その20メートル程先に飼い主が立っていて、「待て」のハンドシグナルを出している。2頭とも微動だにしない。そして、飼い主が1頭を呼び寄せた後に、もう1頭を呼び寄せたのである。う~ん、2頭別々の「呼び戻し」は、なかなか出来るものではない。
その翌日、また公園を歩いていると、正面から先の小型犬と飼い主がやって来た。軽く会釈でもしようと思っていたら、すれ違いざま2頭にものすごい勢いで吠えかかられてしまった。当の飼い主はというと、犬を叱るわけでもなく、僕に謝るわけでもなく無言のまま通り過ぎてしまった。多分、この飼い主は、「スワレ」や「マテ」などの指示に忠実に従わせることが「しつけ」だと思っているのだろう。
いまだに「しつけと「訓練」が混同されているが、上記の「待て」からの呼び戻しは「訓練」で、人や犬に向かって吠えないというのが「しつけ」です。いくら飼い主のいうことを忠実に聞いても、人に迷惑をかけていたら何の意味もありません。
しつけとは、子供と同じように「やっても良いこと」と「やってはいけない」ことを教えることです。その犬のしつけには、飼い主の「道徳観」と「価値観」が大きく左右するのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年6月11日 09:56





横浜市の犬のしつけレッスン/今すぐやめよう間違った「待て」の教え方

犬のしつけの定番と言えば、「お座り」と「待て」ですね。ヴィッセでは「待て」と命令調ではなく、子供に言うように優しく「待って」と言います。これが警察犬の訓練になると、「待てえ!!」とドスの効いた声で威圧感を持って言わなければなりません。なぜなら警察犬の訓練には、「緊張感」と「集中力」が求められるからです。
しかし、家庭犬のしつけに「緊張感」も「集中力」も、そして「厳しさ」も必要ありません。家庭犬の暮らしはリラックスが基本ですから。ヴィッセに来られた飼い主の方々の「待って」の教え方に共通していることが必ず三つあります。一つ目は、画像のように犬にオヤツを見せて「待て」をさせます。当然犬はオヤツしか見ていません。
これを行ってしまうと、犬はあなたのために待つのではなく、オヤツのために待つ犬になります。そして、同時に食べ物に対する「執着心」を育ててしまう結果になります。
二つ目は、犬が待っている間一切褒めません。皆さん「無言」か「待て」を連呼するかのどちらかに分かれます。犬が大人しく待っているということは=「正解」ということです。それを「グ~ド!」と褒めてあげないと、犬は自分の行動が正しいのか間違っているのか不安になります。
この「グ~ド!」は、褒めるニュアンス以外に「そうだよ、それで合ってるよ!正解だよ!」という意味があります。こうして待ってを教えると、犬が安心して楽しく待つようになります。
最後に三つ目ですが、皆さん犬が座った状態で「ヨシ」と言ってオヤツをあげてしまいます。これは「良くできたね!」の「ヨシ」になってしまいます。「ヨシ」は褒めるための言葉ではありません。「ヨシ」は「もう動いてもいいよ」という「解除」の言葉なのです。
そして、待ってを解除した後に、たくさん褒めてあげます。「待って」と「ヨシ」は、セットで教えなければならないのです。一番肝心なことは、外でもできるように応用することです。家で出来ても外や興奮した時は、「待って」ができないという方がほとんどです。ですので、ヴィッセでは以下の「3種類の待って」を教えています。
① 一時待機の待って☞一般的な待ってがこれですね。
➁ 緊急の待って☞リードや首輪が外れた時に命が救えます。
➂ 帰って来るからねの待って☞犬をお留守番させるときに使います。
➂は、出かける時には声をかけずに、無言で出て行くというのがありますが、犬は余計不安になるので、ちゃんと「帰って来るから待っててね」と、声をかけてあげてください。また、ご飯を床に置いて「待って」をさせる方がいますが、これは犬に強いストレスをかけるので行わない方が良いです。
「待って」は、我慢をさせるのが目的ではなく、吠える事も含めて犬が興奮した時やパニックになったりした時に、「行動の鎮静剤」として犬の動きを止めるために使うのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年6月 2日 08:54





横浜市の犬のしつけ教室/しつけと訓練の違い
 「ヤフー知恵袋」で見つけた質問です。あまりにも面白かったので紹介します。
「ヤフー知恵袋」で見つけた質問です。あまりにも面白かったので紹介します。
『○歳○か月の♂の小型犬を飼っています。以前から噛む癖と見知らぬ人に吠える癖が酷いので、訓練所に預けました。家に帰ってしばらくはおとなしくしていたのですが、3週間くらいたつと全く元に戻ってしまいました。しつけ教室の効果なんてこんなものなのでしょうか? それとも悪徳業者に引っかかってしまったのでしょうか?』
訓練所に預けて家に帰ったら、元に戻ったというよく聞く話ですが、訓練所に入れられた犬は、「服従訓練」と呼ばれるものを受けます。この「服従訓練」とは、指示された命令に忠実に従わせることで、犬を服従させ「主従関係」を築くことを目的としています。訓練以外の時間は犬舎に入れられ、徹底的に生活を管理されています。自由な時間はほとんどありません。
訓練の時間が人間と触れ合うことができる唯一の時間で、毎日訓練に明け暮れている訳ですから、当然訓練士の言うことは、よーく聞くようになります。そして、犬が家に帰ると、しばらくは訓練所での生活のリズムが残っているので大人しくしていますが、毎日訓練ずけだった日々から、
以前と同じ自由な日々の生活環境で暮らし、飼い主が何も学んでいなければ、日が経つにつれ元に戻るのは当たり前の話です。まして、相手は生きものなのです。ものを修理するような訳にはいかないのです。僕も日中、犬を預かってレッスンをするので、「犬を預けると先生のいうことは聞いても、飼い主のいうことは聞かないのではないでしょうか?」という質問はよく受けます。
先日、ご夫婦で問題行動のカウンセリングを受けられた奥様から、同じ質問をされました。すると、傍にいたご主人がすかさず、「もしそうなったら、俺たちが駄目だってことだよ」と、奥様に言ってくれたのです。僕は思わずご主人に拍手をしてしまいました。
しつけ教室は「基礎」を学ぶところです。私たちがどんなに犬をトレーニングしても、飼い主がトレーナーから学んだことを、日常生活という「応用」の場で「実践」できなければどうにもなりません。犬(子供)がどう育つかは、すべては飼い主(親)次第なのです。
育てたように子は育つbyあいだみつお
(DOG SCHOOL Visse)
2025年5月27日 09:24





横浜市の犬のしつけレッスン/犬がチャイムに吠えるのは何故?
先日、ヤフーで見つけた記事に、犬がチャイムに吠える理由を以下のように解説していました。
✔知らない人に警戒している
✔飼い主に知らせたい
✔嬉しくて興奮している
✔大きな音に刺激されてしまう
まあ、吠える理由はこんなところだと思います。僕の見解はちょっと違います。
なぜチャイムに吠えるのかというと、
まず一つ目は、「たまに鳴るから」です。
普通の家庭で1日に何回チャイムが鳴るでしょう? せいぜい1~2回? 多くても2~3回くらいではないでしょうか?もしチャイムが1分おきに鳴っていたら、多分20分~30分後には、吠えなくなっているのではないでしょうか? これを「馴化」と言います。
僕はレッスンでこのチャイムに吠える話が出ると、必ず生徒さんに聞くことがあります。それは、「船酔いは何でするのでしょうね?」という質問です。すると、大抵の生徒さんが「三半規管が弱いから」と答えます。
間違いではないですが、僕は、「たまに乗るからです」と答えます。もし、あなたが漁師に転職して船に乗り始めたら、多分1~2週間くらい吐き続けると思います。でも毎日乗っていれば、先程の三半規管が鍛えられますから、いずれ吐くことはなくなるでしょう。
犬の車酔いも同じで、毎日乗せなければ、たまに乗っても車酔いを克服することはできません。そうです、「何か」に慣れさせるというのは、毎日の作業なのです。たまに行ってもその「何か」には、慣れることはありません。
次に二つ目は、「犬には、今何時という時間の概念がないから」です。
もし、あなたの家のチャイムが夜中の2時になったら、当然「誰が来たんだ!?」と警戒しますよね? 最近、僕の家のチャイムが夜の11時半ごろに鳴ったので、僕と妻はびっくりして顔を見合わせました。そして、恐る恐る応答すると「ウーバーイーツです!」と返事がありました。
ウーバーイーツさんが間違って僕の家に配達に来たのです。僕はホッとすると同時に、ちょっと切れ気味に「注文してませんよ!」と答えてしまいました。もし、これが日中のチャイムだったら、ほとんどが宅配の人なので、恐る恐るインターホンに出ることはありませんよね。
私たち人間には、時間の概念があるので、日中のチャイムに警戒することはありませんが、犬には、今何時という時間の概念がないので、常に警戒態勢を敷いているという訳です。以上が僕の見解でした。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年4月 3日 07:48





横浜市の犬のしつけレッスン/犬は何故チャイムに吠えるのか?

犬はなぜチャイムに吠えるのでしょうか?
ヤフーで見つけた記事に、犬がチャイムに吠える理由を以下のように解説していました。
✔知らない人に警戒している
✔飼い主に知らせたい
✔嬉しくて興奮している
✔大きな音に刺激されてしまう
まあ、吠える理由はこんなところだと思います。僕の見解はちょっと違います。
なぜチャイムに吠えるのかというと、
まず一つ目は、「たまに鳴るから」です。
普通の家庭で1日に何回チャイムが鳴るでしょう? せいぜい1~2回? 多くても2~3回くらいではないでしょうか?もしチャイムが1分おきに鳴っていたら、多分20分~30分後には、吠えなくなっているのではないでしょうか? これを「馴化」と言います。
僕はレッスンでこのチャイムに吠える話が出ると、必ず生徒さんに聞くことがあります。それは、「船酔いは何でするのでしょうね?」という質問です。すると、大抵の生徒さんが「三半規管が弱いから」と答えます。
間違いではないですが、僕は、「たまに乗るからです」と答えます。もし、あなたが漁師に転職して船に乗り始めたら、多分1~2週間くらい吐き続けると思います。でも毎日乗っていれば、先程の三半規管が鍛えられますから、いずれ吐くことはなくなるでしょう。
犬の車酔いも同じで、毎日乗せなければ、たまに乗っても車酔いを克服することはできません。そうです、「何か」に慣れさせるというのは、毎日の作業なのです。たまに行ってもその「何か」には、慣れることはありません。
次に二つ目は、「犬には、今何時という時間の概念がないから」です。
もし、あなたの家のチャイムが夜中の2時になったら、当然「誰が来たんだ!?」と警戒しますよね? 最近、僕の家のチャイムが夜の11時半ごろに鳴ったので、僕と妻はびっくりして顔を見合わせました。そして、恐る恐る応答すると「ウーバーイーツです!」と返事がありました。
ウーバーイーツさんが間違って僕の家に配達に来たのです。僕はホッとすると同時に、ちょっと切れ気味に「注文してませんよ!」と答えてしまいました。もし、これが日中のチャイムだったら、ほとんどが宅配の人なので、恐る恐るインターホンに出ることはありませんよね。
私たち人間には、時間の概念があるので、日中のチャイムに警戒することはありませんが、犬には、今何時という時間の概念がないので、常に警戒態勢を敷いているという訳です。以上が僕の見解でした。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年2月28日 10:37





横浜市の犬のしつけレッスン/今すぐやめよう間違った「待って」の教え方。

犬のしつけの定番と言えば、「お座り」と「待て」ですね。ヴィッセでは「待て」と命令調ではなく、子供に言うように優しく「待って」と言います。ヴィッセに来られた飼い主の方々の「待って」の教え方に共通していることが必ず三つあります。
一つ目は、画像のように犬にオヤツを見せて「待て」をさせます。当然犬はオヤツしか見ていません。これを行ってしまうと、犬はあなたのために待つのではなく、オヤツのために待つ犬になります。そして、同時に食べ物に対する執着心を育ててしまう結果になります。
二つ目は、犬が待っている間一切褒めません。皆さん「待て」を連呼するか「無言」か、どちらかに分かれます。犬が大人しく待っているということは=正解ということです。それを「グ~ド!」と褒めてあげないと、犬は自分の行動が正しいのか間違っているのか不安になります。
この「グ~ド!」は、褒めるニュアンス以外に「そうだよ、それで合ってるよ!正解だよ!」という意味があります。こうして待ってを教えると、犬が安心して楽しく待つようになります。
最後に三つ目ですが、皆さん犬が座った状態で「ヨシ」と言ってオヤツをあげるので、これは「良くできたね!」の「ヨシ」になってしまいます。「ヨシ」は褒めるための言葉ではありません。「ヨシ」は「もう動いてもいいよ」という「解除」の言葉なのです。
そして、待ってを解除した後に、たくさん褒めてあげます。「待って」と「ヨシ」は、セットで教えなければならないのです。
一番肝心なことは、外でもできるように応用することです。家で出来ても外や興奮した時は、「待って」ができないという方がほとんどです。ですので、ヴィッセでは以下の「3種類の待って」を教えています。
① 一時待機の待って☞一般的な待ってがこれですね。
➁ 緊急の待って☞リードや首輪が外れた時に命が救えます。
➂ 帰って来るからねの待って☞犬をお留守番させるときに使います。
➂は、出かける時には声をかけずに、無言で出て行くというのがありますが、犬は余計不安になるので、ちゃんと「帰って来るから待っててね」と、声をかけてあげてください。また、ご飯を床に置いて「待って」をさせる方がいますが、これは犬に強いストレスをかけるので行わない方が良いです。
「待って」は、我慢をさせるのが目的ではなく、吠える事も含めて犬が興奮した時やパニックになったりした時に、「行動の鎮静剤」として犬の動きを止めるために使うのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2025年2月27日 20:24





1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>
« ただいまお勉強中! | メインページ | アーカイブ | ご案内 »